ここから本文です。

~バラバラな組織をワンチームに変える中期経営計画の策定と実行~
オーエーセンター株式会社(福岡県北九州市 サービス業 従業員数120名 資本金1,000万円)
北九州のお土産「ネジチョコ」を製造し、携帯ショップの運営や事務機器の卸売を行うオーエーセンター株式会社は、1985年の創業以来順調に業績を伸ばしてきたが、事業が拡大するに従い組織としてまとまりにくくなっていた。伴走支援を通じてボトムアップからの情報による社長の行動変容や、中期経営計画策定プロジェクトによる取締役の意識改革を図り、組織にも変化が生まれ始めており、海外進出という大きな果実も呼び寄つつある。
本事例のポイント
【全社横断インタビューと社長のリーダーシップ強化】
対話と傾聴の中で、同社の本質的課題は「社員に向けた社長のリーダーシップ強化」と「取締役の職責に関する意識改革」と感じた。そこで、全社横断のインタビューを実施。「社長は遠い存在に感じる」「面談機会は年に1回のみで相談できる相手がいない」「昇格しても待遇面の変化がなく、夢が持てない」などの様々な現場の意見を間接的に社長にフィードバックすることで、新たな気付きが得られるように促した。社長は当初、驚きを隠せない様子だったが、一つ一つの意見を噛みしめるように理解してもらい、実際に自ら行動し社員とコミュニケーションを取ることで腹落ちに繋がった。この体験は社長の行動変容を促し、朝礼やチーム会議に積極的に参加してこれまで以上にリーダーシップを発揮。その後の取組においても円滑に進めるきっかけとなった。
【社長の判断に寄り添い、企業課題の一つ一つを自分事に】
伴走支援の過程で、社長が腹落ちに至ったもう一つのポイントとしては、課題設定の経緯があげられる。抽出した課題全35項目において、「改善余地」と「事業影響の大中小(経営上のインパクトと緊急度)」のランク付けをすべて社長に実施してもらうことで、一つ一つの課題を自分事にしてもらえた。ここからさらに13項目の重点課題に絞り込み、最終的に2つの長期的取組に収斂できたのも、社長自身の判断に寄り添って進めたため十分な納得感を得ることができた。
当社の背景
北九州市で通信事業を展開する当社は、NTT西日本、NTTドコモの代理店として地域密着のサービスを提供してきた。2016年からはフードビジネスも開始し、「モバイル事業部」「システム事業部」「フードサービス事業部」の3つを事業の柱としている。しかし、これらはそれぞれに運営されて情報共有や事業連携がなく、特に急激に業況が沈下しているモバイル事業部は社員のモチベーション低下が生じている状況であった。
また、社長はスポーツマンということもあり、決断が早く行動力のあるタイプだが、NPO法人や産学連携など社外活動も多く、コミュニケーションは社外を中心に行われている印象を受けた。広くボトムアップからの情報を得ることも必要であり、さらに経営陣の間でもより成長するための意識改革が求められる状況だった。
支援の流れ
【社長の経営者像を深堀りし、信頼構築に繋げる】
社長との最初の面談で人柄や家族関係、ライフスタイル、こだわり、尊敬する人物などの考えをじっくり深堀りし、信頼関係の基礎を築いていった。また、社長から過去の取材記事や発行した書籍などの提供があり、支援の折にその内容に触れることで共感を深め、本質的課題についても率直な意見を引き出していくことができた。
【企業の自走化へ繋がる経営陣の意識改革】
企業の自走化に向けての取組は、ボードメンバー5名に中期経営計画策定プロジェクトに参画してもらうことでチームワークの強化と意識改革を狙った。特に自分事にしてもらうために、じっくり考える必要のあるテーマはできるだけ宿題として全員に課し、支援日にその結果を議論する流れを繰り返した。当初は取締役の発言が少なく消極的だったが、徐々にチームワークが醸成。最終的に管掌部門の目標や実行計画を自ら打ち出すなど、大きな成長が見られ、このプロジェクトが企業の自走化へつながる有効な下地作りになった。
【中期経営計画の発表を機に全社員の意識がひとつに】
支援者は常にファシリテーターに徹し、傾聴と対話を繰り返して社長や取締役自身が発する言葉を具体化し納得感を得るように努めた。また、課題解決の段階でプロジェクトメンバーに自分事として協力してもらうことで、実現可能な中期経営計画が策定できた。
さらに、中期経営計画を発表する場として全社会議を実施し、社長自ら熱意をもって企業ビジョンや経営方針を社員に向けて語り掛け、取締役も管掌部門の事業方針について発表。社員は熱心に耳を傾け、支援者からも「会社を変えられるのは、経営者だけではできない。皆さん一人一人が本日の内容をしっかり受け止めて、小さな一歩でもいいので前に進んでください」というメッセージを発信した。支援期間中に財務部長がプロジェクトに参画するようになってからはプロジェクトへの協力体制が一層強化され、全社一丸となってのチームワークが徐々に醸成されていった。
伴走支援の効果
支援で立ち上げたプロジェクトの成果としては、同社がこれまでに策定したことのない中期経営計画の骨子を策定することができた。取組を通じては、現場の打合せに積極的に参加し、自身の言葉で社員へ様々なメッセージを伝えるようになった社長の行動変容が大きい。また、プロジェクト会議の中で徐々に積極的に発言するようになり、全社発表会でそれぞれの事業部方針を伝えるなど取締役の意識改革も見られた。
全社発表会の翌日から、中間管理職が積極的に部門内で議論の場を持つなど社員の変化も見られ、支援期間中に冷凍ケーキの商品開発にも取り組み販売が実現した。携帯ショップにフードサービス事業部の製品コーナーを作って販売する事業連携が図られ、2023年4月には2事業が融合した新たなサテライトショップもオープン。今後、香港、シンガポール、アメリカの3か国への進出も予定している。
|
|
|
閲覧数ランキング
コンテンツフィルタの内容が入ります。

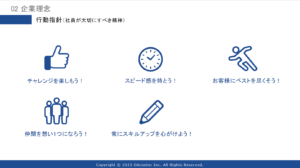


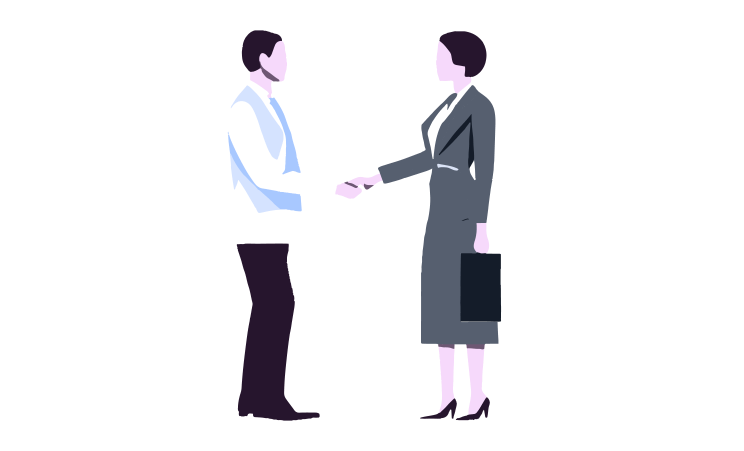

-1568x784.jpg)




