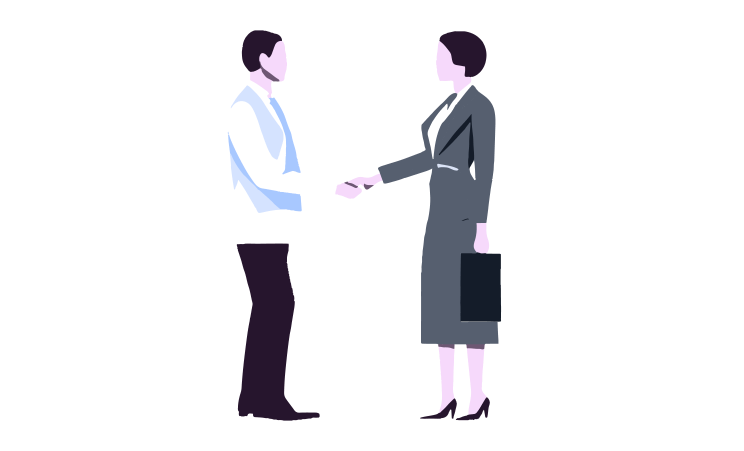ここから本文です。

~大企業向け小品種大量生産から多品種少量生産体制への脱却~
福岡県嘉麻市 製造業 従業員数16名 資本金1,000万円
メーカーが製造した製品を梱包するためのプラスチックケースの生産を行ってきた当社は、得意先の大手企業が製造ラインを海外へ移したことから主力製品の売上が激減。このため、従来の大企業向けの小品種大量生産から顧客のニーズに合わせた多品種少量生産体制へ脱却する必要があった。支援には、「事業性評価」などの専門性を持った中小企業診断士が運営実態を把握し対策を打ち出すとともに、生産管理専門の診断士も加わって多方面から経営の立て直しを図った。
本事例のポイント
【事業性評価専門の診断士による経営診断及び支援】
支援開始に当たり、企業の現状を把握するための経営診断を行った。財務分析及び、知的財産などの非財務項目を見える化するための「事業性評価システム」にて運営実態を確認し、経営改善計画策定を支援した。当面の改善方策として、「営業管理体制の充実」「生産管理体制の見直し」「経理管理責任者の養成」「老朽化設備の更新」「開発中の新製品を活用した環境対応商品の販売」の5つを設定。営業管理体制については外部のネットワークも活用しながら受注を確実にしていき、生産管理体制については福岡県中小企業振興センターの専門家派遣を活用して生産管理の指導を依頼することとした。
【生産管理専門の診断士による支援と専務の意識改革への取組】
当社は専務が主として営業を担当していたが、生産についても社内で一番詳しかった。しかし、支援を進めるうちに生産管理は専務の胸三寸で行っている状態であり、数値化できていないことが判明。専務はこれまで「自分ができることは部下も同じように考えてできるはず」という前提のもと現場に指示しており、生産品種が増すと生産管理が混乱してしまうなど工程は安定しなかった。これらは部下と共通言語でのコミュニケーションができないことが原因であることを専務に理解してもらい、それからは工程の状況を数値で表して業務の見える化を図った。「数値」という共通の言語でお互いに話し合って目標を設定し、細かいところは部下に任せて困ったところだけ相談に乗るという方針に変えたことで、専務と現場の意思疎通がスムーズになり、生産管理体制の改善に繋がった。
当社の背景
2015年の支援開始当時、売上の90%を大手企業向けに製品包装資材としてプラスチックケースの生産を行っていた。しかし、主要取引先が生産拠点を海外に移行し、3億円を超えていた売上が半減。窮地に陥る中、新型コロナ感染拡大の影響により他の取引先からの受注量も減少し、材料価格も高騰するなど厳しい状況にみまわれ、創業以来の苦難に直面することになった。
支援の流れ
【顧客に依存した生産体制から効率的な生産体制へ転換】
これまでは、顧客からの受注の度にやみくもな品種切替を行っていた。このような作業時間の無駄をなくすため、見込生産が可能な上位3品種に絞り、効率的な品種切替ができる「ダブルビン方式」による生産に転換。その結果、残業が大幅に減少した。
また、生産能率の標準が設定されておらず出たとこ勝負の生産であったため、過去の品種ごとの生産実績から生産能率の平均とベストパフォーマンスを抜き出して標準生産能率を設定。さらに生産実績、歩留まり、標準値との差などが品種、生産機械、オペレータ、作業者ごとに分かるデータを即日出せる生産管理システムを構築し、在庫管理まで一括して行うことで在庫を考慮に入れた生産計画も立てられるようになった。
【良品が安定的に流れるための初期品管理の徹底】
従来、最終工程の検査で不良品を取り除くことによって品質をキープしていたことから、品質問題も起こっていた。そこで「品質は検査ではなく、工程で作り込むもの」という考えのもと工程ごとに厳しく管理し、次の工程に不良品を流さないようにした。効率的な品質管理のためには早い段階で不良品を検知することが重要であり、工程の初期になればなるほど厳しい目が必要になる。このことを全従業員が理解し、初期品管理を徹底させて良品が安定的に流れるようになるまで通常生産体制に入らないこととした。
【品種ごとに問題点を抽出し売上改善活動を推進】
主力製品の売上減によって窮地に陥ったため、製品単位の収益管理を可能にするべく、品種ごとの粗利の実績が明らかになるように支援した。これにより、問題となる品種が水面上に浮上。標準を守れなかった理由やベストパフォーマンスとの差などを分析、改良して品質管理システムに残すことで、粗利の少ない品種に対して個別に改善案を立てることが可能となった。また、経理システムの正常化に向けて、月間の品種ごとの売上から月初に前月の簡易の損益見積ができる方策や、試算表のキャッシュフローから直近の資金繰見込が担当者レベルで算出できる方式を検討。他にも、顧客との打合せから受注、設計、顧客承認、金型試作、製品試作といった販売計画の工程をガントチャートで見える化し社内で共有するシステムも構成しつつある。
伴走支援の効果
中小企業診断士による改善計画によって残業が大幅に減るなど、一定の成果を上げるに至った。原材料費の高騰などで依然として苦しい状況ではあるが、バイオプラスチックの開発などにより当社最大の問題である絶対的な売上不足にも目処がつきつつあり、何とか生き延びることができた。これらは、生産管理を現場に任せたことで専務が営業に専念できるようになり、新規受注に注力できるようになったことが大きいと考える。生産管理体制の見える化が図られ、生産上の問題把握と改善がスムーズに行われるようになったことも功を奏している。在庫を把握した正常な試算表に移行でき、今後はキャッシュフローを考慮に入れた資金繰り計画を立てられる状況になってきた。また、これまで行われていなかった経営陣5人と専門家のオンライン会議により情報の共有性が格段に向上。納得のいくまで議論し納得がいったら挑戦するという姿勢を全従業員に広げ、社内改革にも繋げることができた。
閲覧数ランキング
コンテンツフィルタの内容が入ります。