ここから本文です。
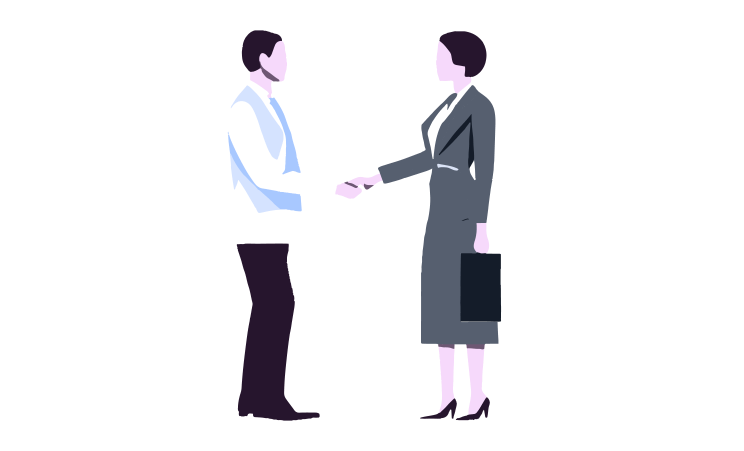
〜変革の機運を後押しし、現場社員の自発的なアクションに繋げる〜
帯広地方卸売市場株式会社(北海道帯広市 食料品卸 従業員数110名 資本金4,800万円)
支援開始当時、当社は経営体制が一新され、新経営陣の間で「社内変革」に向けた機運が高まっていた。これを受けて、経営陣以下、部門・役職横断的なチームを組成。その中で社内の課題の洗い出しを進め、「企業理念の策定」、「社内コミュニケーションの活性化」、「組織・人事制度の改革」といった個別の取組のプロジェクト化を行った。こうした取組は伴走支援終了後も当社によって自律的に継続され、取組の継続を通じて社内のコミュニケーションの円滑化や、若手~中堅社員による自発的なアクションに繋がっている。こうした取組は経営状況にも反映され、支援終了後も増収・増益を実現している。
本事例のポイント
【信頼関係の構築】
当社はこれまで外部コンサルを活用した経験がなかったことから、支援者として、事前のリサーチやチーム内の協議をしっかりと行い、当社の自己変革に向けて真剣に考えているとの思いを伝えることを心掛けた。訪問時にはコンサルタントが主体となって企業との対話を進めながら、支援チームのメンバーである市や金融機関の職員も発言し、支援チーム全員が当事者意識をもって支援に臨むことを重視した。当社はこれまで、外部のコンサルを活用した経験がほとんどなかったことから、支援開始当時は、あたかも「外国人」が来たかのようであったが、「支援チームとして、当社がどうすればよくなるかを真剣に考えている」という真剣な姿勢を示すことで、経営者との信頼関係構築に繋がった。
【社内の機運を捉えた後押し】
支援開始当時、当社は経営体制が一新され、新経営陣が「社内変革」について強い問題意識を持っていた。その意識や思いをしっかりと汲み取りながら対話を行い、部門・役職横断的なプロジェクトチームの組成や運営の支援を通じて、経営陣の思いを現場レベルでの行動に結び付けていった。
当社の背景
当社は大正2年(1913)年に創業した「百年企業」である。野菜、果実、水産、食肉、花卉等の幅広い商品を扱い、営業冷蔵庫、加工配送・リサイクル施設を備え、十勝地域の「食」の流通を担ってきた。しかしながら、少子高齢化に伴う地域商圏の縮小や、卸売市場を介さない直取引の増加といった外部環境の変化により、近年の売り上げは減少傾向にあった。
また、当社は経営陣を含め「プロパー社員」が大多数であり、人事異動も殆どなく、業務が属人化しがちであり、支援開始当時、社員同士の人的交流は非常に盛んである反面、仕事ベースでの部門間コミュニケーションは希薄な状態であった。
支援の流れ
【社内変革の「きっかけ」として伴走支援を活用】
当社が、取引先の金融機関からの紹介を通じて伴走支援の存在を知った当時、当社は社長の交代を機に経営体制を一新し、「外部環境が変化する中で、当社も変化しなければならない」といった問題意識が高まっている状況にあった。他方、社内変革について、どこから、どのように手を付けていくべきかが、新しい経営陣の悩みだった。
「変革が必要だと言っても、社内での自発的な動きをゼロから作っていくことは容易ではない。また、外部の知見を使うにしても、そもそも当社はこれまで外部のサービスを使った経験も殆どないことから『わざわざ費用を投じる必要性はどこにあるのか? 効果はあるのか?』といった抵抗意見が出てきてしまうのではないか。まずは費用負担のない伴走支援を、一つの『きっかけ』として使ってみてもいいのではないか」
そのような意見もあり、伴走支援の申込みに至った。
【支援者として「会社のことを考えている」真剣さを伝える】
本支援では、担当のコンサルタントのほか、金融機関及び市の職員で支援チームを組み、訪問を行った。当社はこれまで、外部のコンサルを活用した経験がほとんどなかったことから、あたかも「外国人」が来たかのようで、初期の関係構築はお互い手探りの状態だった。
その中で、チームとして大事にしたのは、しっかりと訪問前に事前のリサーチや支援チーム内での協議を重ね、「支援チームとして、当社がどうすればよくなるかを真剣に考えている」ことを熱意として示すことだった。
また、コンサルタント・金融機関・市という混成チームで支援に臨む際、コンサルタントのみが発言し、その他のメンバーが同席・傍聴するだけでは、「なぜこの人はこの場にいるのだろう」という印象を与えてしまう。
このため、各訪問時にはコンサルタントが主体となって企業との対話を進める一方で、市や金融機関の職員もしっかりと発言し、支援チームの全員が当事者意識をもって支援に臨んだ。
【部門・役職横断的なチームアップを通じて課題解決の素地を醸成】
課題の設定に際しては、社長や幹部陣だけでなく、現場の社員も巻き込んだプロジェクトチームを組成し、幅広い観点から当社全体の課題の洗い出しを行った。その際、出席者それぞれが自分事として捉えてもらえるよう、出席者の発言量の多さ、少なさも見ながら、どこが課題と思っているか、どうしていくことが必要か、議論を進めた。
しかし、当社はそれまで人事異動も殆どなく、情報共有がほとんどなく、社内のメンバーはこうしたプロジェクトチームで動くこと自体が殆ど初めての経験である。そもそも何を話せばよいのか、また、経営層や他部門のメンバーもいる前で自分としてどこまで発言してよいものか、慣れない部分も大きかった。そのため、専務からも、「公式な話ではない、各人が思っていることをざっくばらんに話してもらって構わない」と発言を貰い、参加者が発言しやすくなる空気感を作るとともに、あえて支援者側からも攻めた発言をすることで、「そんなことまで言っても良いのか」といった、心理的安全性を高める工夫も行った。
また、部門だけでなく、ベテラン、若手を問わず役職をまたがったチーム編成としたのもポイントである。
各部門のベテラン社員は、それぞれ長年その分野に携わっており、それぞれの分野における「プロフェッショナル」としての自負がある。「課題はどこですか、どう思いますか」という問いに対して、若手社員も出席している手前、おいそれと「分からない」とは言えない。出席者のこうした立場や思いも汲み取りながら、プロジェクトチームの運営を進め、「企業理念の策定」、「社内コミュニケーションの活性化」、「組織・人事制度の改革」といった個別の取組プロジェクト化に繋げていった。
伴走支援の効果
上記のプロジェクトチームの活動は一過性のものにとどまることなく、伴走支援の終了後も、情報発信やセカンドキャリア形成といったプロジェクトに派生している。こうしたプロジェクトについても、経営層のトップダウンではなく、若手~中堅社員による自発的なアクションに繋がっているのが大きな特徴だ。
こうした取組を通じて、部門間のコミュニケーションも活発化してきた。これまでは自部門の状況だけ見ておけばよいという考えが、例えば管理部門では電気代や運賃がこれだけかかっている、赤潮でこの海産物が打撃を受けているといった、他部門の問題にも意識が向くようになってきた。また、内部的な問題意識だけでなく、「他の会社には販売マニュアルがあるが、当社にはそういったものは必要ないのだろうか?」といった、外と比較した問題意識も高まりつつある。こうした取組は経営状況にも反映され、支援終了後も、2022年12期にて、取扱高4.6%増、経常利益13.6%増を実現している。
閲覧数ランキング
コンテンツフィルタの内容が入ります。








