ここから本文です。

〜「気づき」と「旗振り」で第一歩を踏み出すきっかけを与える〜
奥野工業株式会社 (愛知県高浜市 輸送機器部品製造業 従業員数160名 売上35億円 資本金4千5百万円)
当社は、DXに向けた取組を実施しようとしたものの何から取り組めばよいかわからず、最初の第一歩が踏み出せない状況にあった。そこで支援者は、経営者/従業員に対し、問答法を取り入れた対話と傾聴を重ねることで、本質的な課題を追求し、「論点や考えを整理しながら、議論をまとめていく進め方」を当社に教授し、「自ら考える」ように誘導した。結果、DXに向けた方針と取り組むべき事項を当社自らが見出すことができ、DXに向けた最初の第一歩を踏み出すことができた。こうした取組により、従来のトップダウン経営から現場の意識や発想を取り入れたボトムアップ型の動きが生まれ、自己変革できる会社として自走化につながる大きなきっかけとなった。本事例のポイント
【真の課題の識別】
当社において取り組むべき課題は会社として明確に表明されていたが、それは当社として対応すべき事項に過ぎず、「課題」そのものではなかった。そこで、支援者は、「なぜ?なぜ?」と質問を深める問答法を通じ、当社として対応すべき事項の裏に隠れた真の課題や「じっくり考える」という組織風土を当社に気づかせるとともに、「論点や考えを整理しながら、議論をまとめていく進め方」があることに気づきを与えた。
当社の背景
当社は油圧シリンダー、プレス加工品、樹脂成型品、レッカー車を製造。高い技術力と一貫生産体制ができる強みを持っており、株式会社豊田自動織機、株式会社デンソーなど大手メーカーを主要顧客としている。設立は1961年。長年にわたり顧客の信頼と期待に応え続けてきた結果、「お客様の依頼を早急に解決することが最優先」、「トップダウン型の経営」という社風が長く続いていた。
支援の流れ
【当社のおかれている状況を把握する】
支援者はまず、経営者にヒアリングを実施し、経営者サイドで感じている課題を確認した。その結果、生産性改善(生産の仕組みづくり/DX)と新商品の開発促進の進め方について悩んでおり、特にDXについては、デジタルリテラシーを有した人材が不足していたことも相まって、会社として何をすべきかわからず、具体的な取組に向けた最初の一歩が踏み出せない状況にあった。
また、当社の社風から、課題解決において、短期的なその場限りの対応となることが多々あり、今回のDXについても、現場の意見を確認しないまま、ベンダーから新しいシステムを購入するが、現場が使いづらいシステムで使わなくなるという懸念があった。
【真の課題を特定する】
支援者は、当社でDXに向けた最初の一歩を踏み出せない状況をもたらした要因は何かと考えた。
名だたるメーカーを顧客とし、顧客からの依頼を早急に解決できる技術力や対応力があるにも関わらず何故できないのか。行きついた答えは、「お客様の依頼を早急に解決する」という社風の存在であった。
つまり、顧客からの依頼という対応すべき事項が常に明確な状態に慣れてしまい、「ゼロから対応すべき事項を自身で考え、創造する」という発想が社内で欠けてしまっていたことが、DXに向けた最初の一歩を踏み出せない原因であったのである。それは、新たな生産の仕組みづくりや、新商品の開発促進といった、経営者が考える他の課題でも同様であった。
そこで、支援者は、経営者に対し、当社が抱える真の課題は、DX/生産の仕組みづくり/新製品の開発促進が上手くいかないという表面的なことでなく、創造を行うために「じっくり考える」という組織風土が存在していないことであることを指摘し、「考え方を身につけること」が自己変革力の向上に向けた課題解決の方法であることを提案した。
【会社に「気づき」を与えるための「旗振り」をする】
支援者の提案を受け、後継者たる取締役副社長を筆頭に、経理、生産管理、製造からそれぞれ社員を抜擢し、計6名のプロジェクトチームを組成。さらに、経営陣と現場の橋渡しができるよう、代表取締役副社長がアドバイザーとして参画。
プロジェクトチームに対しては、支援者がモデレーターとなり、会社が考える課題に即したテーマの提示や質問を繰り返し実施。また、将来の動向をどう考えるか、当社としての強みや弱みは何か、収益性や将来性をどう考えるかなど、経営者目線で考えざるを得ない内容も意識して提示された。
特に、DXの目的として売上を伸ばしたいのか、生産性を向上させたいのかという問いは、副社長において、会社が利益をあげていくために必要なことは何かということを、データをもとに分析し始めるきっかけにもなり、役員会においてもデータに基づく議論がなされるという行動変容にもつながった。
こうした支援者による問答法が繰り返されるうちに、従業員達は経営者から見てもイキイキするようになり、やがては、考え議論することが「おもしろい」「視野が広がった」と言う声も自然に出始めた。
さらには、「論点や考えを整理しながら、議論をまとめていく進め方」が、社内プロジェクトを進める際や、従業員を教育することに効果的な手法であるとの認識を経営者自身も持つに至り、最終的に、当社としてのDXとして、まず社内システムの改変から取り組むことが決定された。
さらに、仕事が属人化し従業員同士の横のつながりができていなかったことや、特定の課題だけに対応するあまり全体の根本的な課題に目が向かないといった問題点を当社自身で識別し始めようになるなど、「自ら考える」社風が醸成された。
閲覧数ランキング
コンテンツフィルタの内容が入ります。
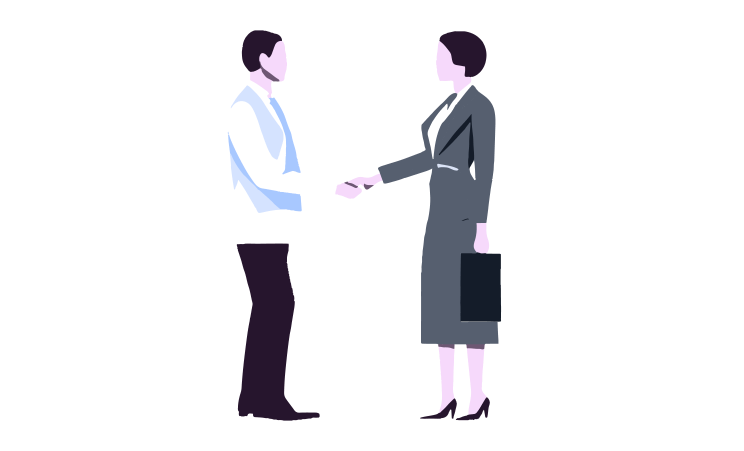




-1568x784.jpg)



