ここから本文です。

~社員の主体性の醸成で次なる成長のステップへ~
株式会社南雲製作所(新潟県上越市 製造業 従業員数113名 資本金9,500万円)
当社は、プロパーの現社長が創業家の先代社長から経営を引き継ぎ、業績アップを図ってきた。生産管理コンサルタントなど外部リソースも活用し成果を出していたが、経営に対する社員の主体性の欠如が、さらなる成長を妨げる要因のひとつとなっていた。社員の主体的活動を促し、自ら問題意識を持って課題に取り組む経験や、部門横断プロジェクトを通じて最適解を導く経験を積んでもらうことで、強いリーダーシップに頼る体制からの脱却を図った。
本事例のポイント
【本質的課題に対する社長の腹落ち】
当社は中小企業庁の「元気なモノ作り中小企業300社」に選定されるなど数々の表彰歴を持つ優良企業だが、社長は危機意識が強く「課題はいくらでもある」との認識だった。課題設定支援を重ねる中で、当社の表面的な課題の奥に潜んでいる「本質的課題」を率直に伝えた打合せがターニングポイントとなり、伴走支援、および当チームへの信頼が飛躍的に高まった。本質的課題は社員の主体性と、外部リソースに対する会社の主体性が欠けていることであると伝えたところ、社長はストンと腹落ちされたようだった。
【本質的課題と表課題のリンク】
表課題の解決支援を通して、本質的課題の解決につながるように課題設定をした。また、表課題は、製造業としての業績向上という成果にもつながるものを意識して設定した。
当社の背景
当社は、金属プレス用精密金型の設計製作会社として半世紀以上の実績を誇る。高難易度のものに果敢にチャレンジする技術指向が強く、加工設備の保有数は金型メーカーでは国内有数であり、社員の多くが様々な技能資格を取得している。創業家の先代社長からバトンを渡され、2016年に現社長が就任。強いリーダーシップのもと順調に業績を伸ばしてきたが、経営に対しては常に危機感を持ち、社長自ら毎年年度ごとの課題と目標を記した「経営のしおり」を作成。その課題に沿って、リーダー以上の社員は個人目標を設定し取り組んでいる。半面、社長の強い統率力と目標必達の方針もあり、社員には「言われたことをやればよい」という受け身の雰囲気が蔓延していた。
支援の流れ
【表面的な課題の奥に潜んでいる本質的課題の提示】
初めに当社課題の総点検を行い、総点検終了後、抽出された課題を図にして全体感を示した。社長は「内容はその通りであり異論はない」と理解を示すものの、この時点で深い信頼関係を築くには至らなかった。対話と傾聴を重ねる中、社長から「製造業でよく言われるQCD(品質・コスト・納期)の改善などの課題提案では従来型の支援と変わらない」という意見が出された。「伴走支援では隠れていた重要な課題を支援して欲しい」との要望もあり、支援チームがかねてから着目していた本質的課題を提示した。
1つめは「社員の主体性の欠如」。社員自らがアクションを起こすことがなく、これには社長の強い統率力が遠因にもなっていると率直に述べた。先代社長から経営を受け継いだときは強いリーダーシップが必要な時期であったと思われるが、今後さらに成長して次のステージに行くには、社員が主体的に動くことが必要である。また、当社は以前生産管理のコンサルタントを受けて生産効率を大きく改善しているが、その管理方法は教えられた内容からまったく進化していない。大事なのは活用後であり、コンサルから学んだことを起点に自社で工夫改善し進化させようとする部分が弱いのではないかと伝えた。
2つめは「中期的取組の必要性」。社長が作成している「経営のしおり」は素晴らしい内容であるが、取組は年度ごと単年のものであった。当社は技術指向の強い会社であるので、将来の糧となる新たな技術獲得を常に視野に入れておくことが重要となる。ただし技術獲得を単年で完結することは現実的には難しいこともあり、こうしたテーマの設定はなされていなかった。中期的視点で将来必要となる技術を獲得していく取組が必要と伝えた。
【本質的課題とリンクした表課題の設定】
課題設定においては、表課題の解決支援を通して本質的課題の解決につなげることを意識した。また、表課題は、製造業としての業績向上という成果にもつながるものとした。社長以外に、製造部と技術部の責任者を兼務している若い取締役が当伴走支援の担当者責任者になっていたので、全体を通してこの2人が主体的に行動し育成につなげることを常に意識した。
表課題と本質的課題に対する狙いは、「技術開発ロードマップの作成」「生産リードタイムの短縮」「基幹情報システムの見直し」の3つ。若い取締役が主導して作成したものを社長に提案し承認を得て、中期的スパンで課題に取り組む経験を全社的に積むこと。製造部の課長たちが主体となって改善活動を実施し、社員の主体性を醸成すること。これまでやったことのない部門横断的なプロジェクトを実施し、部門ごとに抱える問題や考えを理解し議論することで最適解を導く経験を積むことが大事であると提案した。
【課題解決に向けた社員主体の進め方を支援】
「技術開発ロードマップの作成」については、これまで漠然としていた「当社が将来に向けて狙う市場とそれに必要な技術の方向性」を明確にした。どの分野をターゲットとするかは営業部とも擦り合せを行いながら進め、実際のロードマップ作成にあたっては、フォーマットや検討すべき項目を示し、それに基づいて企業側で作成した。
「生産リードタイムの短縮」は、生産現場で発生している停滞を含めあらゆるムダが改善の対象となる。まずは、生産現場のムダを認識するところから改善を進めた。当社にとっては当たり前のことも外部の目で見ると疑問に思うことなどは率直に伝え、変えることも検討してもらった。生産の現状を把握していない部分も散見されたので、現状把握をできるようにして、そのデータから自分たちで課題を見つけ解決していくことを促した。
「基幹情報システムの見直し」は、ITに精通しているコンサルタントに加わってもらい支援を進めた。継ぎ接ぎのシステムを見直して将来的にはシームレスなシステムを見据え、各部門に残っている業務のムダを抽出し、新システムではそれらの解消を図った。経験のない部門横断的なプロジェクトだったため、最初は意見も出なかったが、回数を重ねるうちに活発な議論となった。なお、課題解決に社長は参加せず、それぞれのメンバーに任せるようにした。ただし、毎回の支援の状況を支援チームから直接報告することで、社長の考えや想いを確認するなどコミュニケーションを図った。
伴走支援の効果
一番大きいのは、社長の意識の変化と、それをすぐに行動に移してくれたことである。具体的事例としては、社長が「経営者としては次世代育成、技術を初めとした中長期スパンの道付けが私の最後の仕事かもしれない」と発言されたこと。伴走支援について社員に資料を配布し、中長期に向けた活動として「社員の主体性の醸成」や「現場主導型の経営体制の構築」に取り組んでいることを説明し、全社で目的を共有したこと。加えて、当伴走支援の担当責任者であった若い取締役が、課題解決の手法や主体的活動を経験することで成長したことも大きい。
また、技術開発ロードマップを作成し、技術開発の方向性を明確化したことで、関連技術として新規開発案件が発掘できるなど営業面にも効果が波及している。生産リードタイムは従来8週間のものを6週間に短縮でき、生産現場においてもメンバーの何人かは、自分で課題を見つけ改善策を講じるなど主体的行動が見られた。今後は現場社員主体による改善活動の推進も期待できる。さらに、新・生産管理システムを導入したことで業務効率も大きく改善。生産管理コンサルの教えをシステムに置き換えることで、課長クラスの8人が毎日2時間かけていた日産計画の作成から解放され、今後の更なる業務効率アップに向けてIT担当部署が新設された。社員の主体性向上がゆっくりではあるが見て取れ、今後の継続的改善が期待できる。
業績面では、コロナの影響を受けた売上も回復し、営業利益率は前年比4.2%アップ。営業や技術体制強化に向けて社員を増員しており、ここ3年の社員数は、102人、108人、113人と推移している。
|
. |
. |
閲覧数ランキング
コンテンツフィルタの内容が入ります。




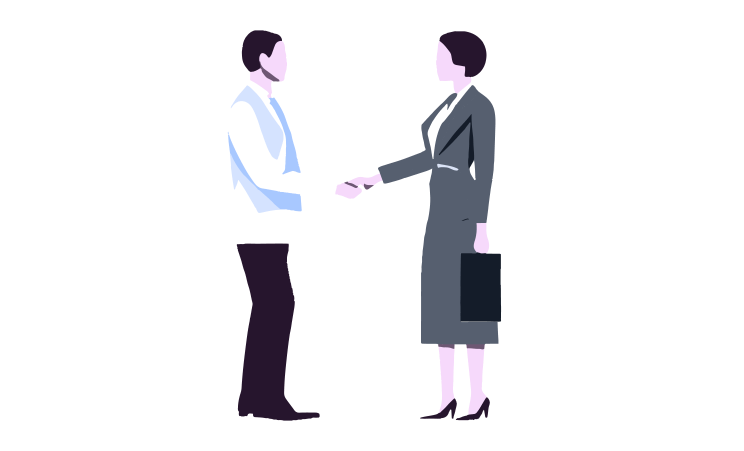
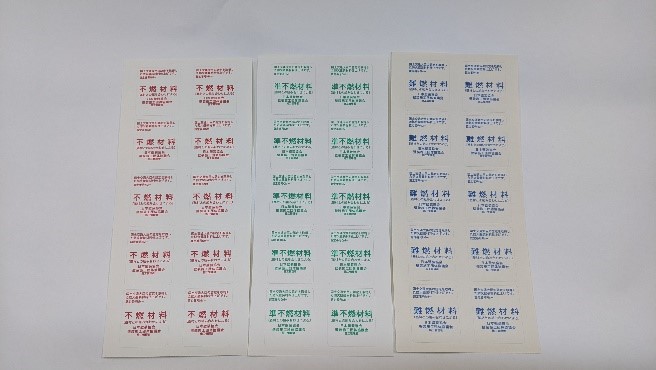


-1568x784.jpg)



