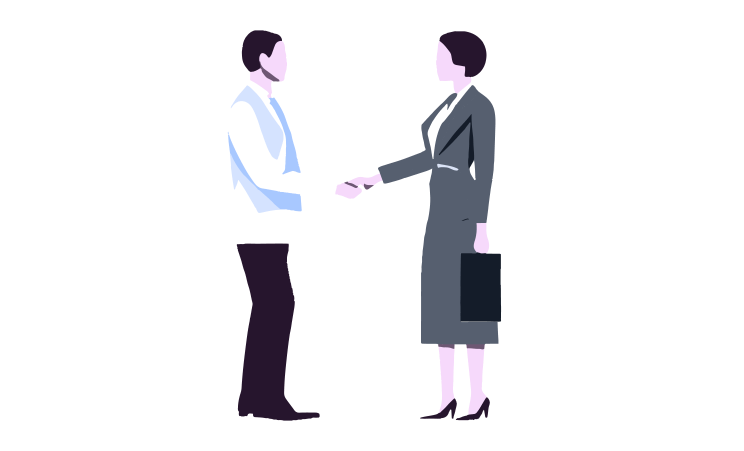ここから本文です。
ノウハウ特集
経営者の気づき・腹落ちを得るには
本質的な課題に事業者自らが気づき、腹落ちするためには対話と傾聴をベースとしつつ、事業者自身の口で課題を言語化してもらうことを意識します。事業者自身が課題を言語化できれば、無意識から意識的な考えに変換され気づきが生まれます。結果として、事業者自らが本質的な課題を特定したと実感し、自分事としての納得感を醸成できるようになります。ここでは、そうした支援ノウハウを紹介します。
-
■『なぜ』という質問を繰り返す
事業者の抱えている問題は、表面的な事象だけに目を向けても捉えきれないことがあります。捉えている事象を「結果」と「原因」に分別し、さらに、その「原因」を様々な角度から深堀りしていくことで、問題の真因を見つけ出すことができ、本質的な課題への気づきとつながります。
上記事例では、取り組むべき課題は明確に表明されていましたが、それは当社として対応すべき事項に過ぎず、「課題」そのものではありませんでした。支援者は、「なぜ?なぜ?」と質問を深める問答法を通じ、対応すべき事項の裏に隠れた真の課題や「じっくり考える」という組織風土の重要性について気づきを促すことができました。
参考事例はこちら
〜「気づき」と「旗振り」で第一歩を踏み出すきっかけを与える〜
- DX
- 自走化
-
■論点を投げかけて、経営者に課題感を口に出してもらう
事業者が感覚で問題意識を捉えている場合、問題が構造的に整理されず、本質的な課題にアプローチすることができません。対話と傾聴をベースとしつつ、事業者自身の言葉で課題を言語化してもらうよう支援者が誘導する必要があります。また、行われた対話をふり返られるよう、議事録を残しておくことも重要です。
上記事例では、経営者が抽象的な課題意識を多く抱えており、それらを言語化し、具体化していくことに難しさを感じ、解決に落とし込めずにいました。支援者は経営者が抱える課題意識の背景を認識したうえで、現場の○○という状況を把握しているか、従業員はどのように感じていると思うか、自身はそれについてどう考えるかなど、気づきを与える質問を繰り返し、経営者自らが答えにたどり着くよう誘導しました。
参考事例はこちら
〜会社自らで解決策を見出せるよう、相談役に徹する〜
- 信頼関係構築
- 後継者育成
閲覧数ランキング
コンテンツフィルタの内容が入ります。